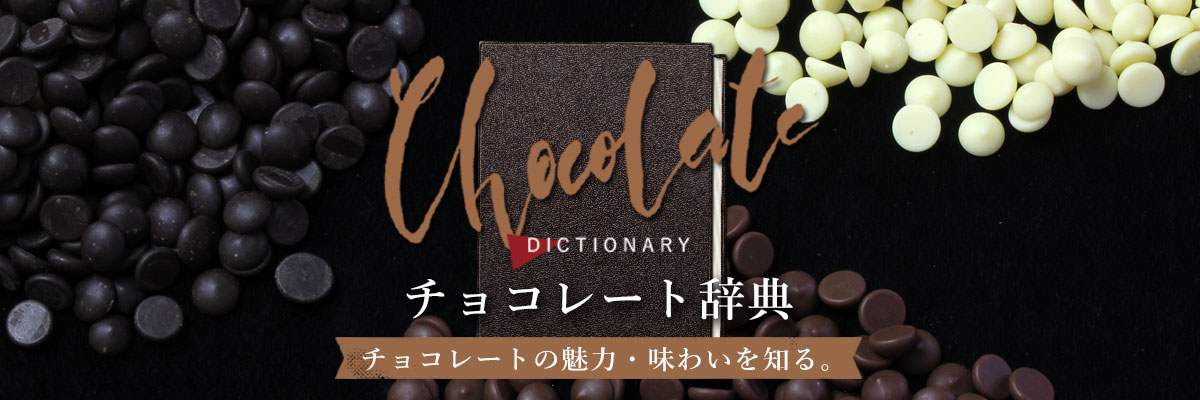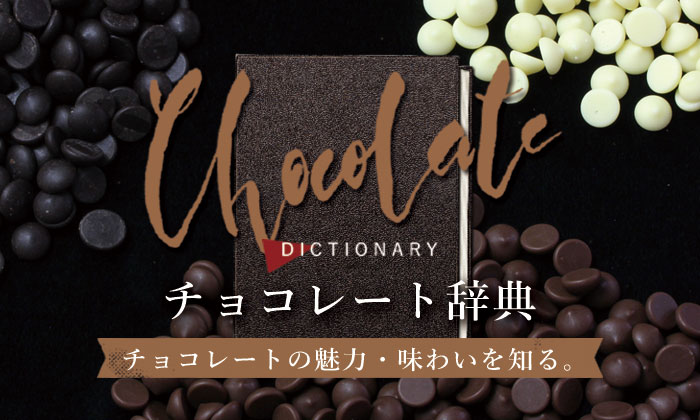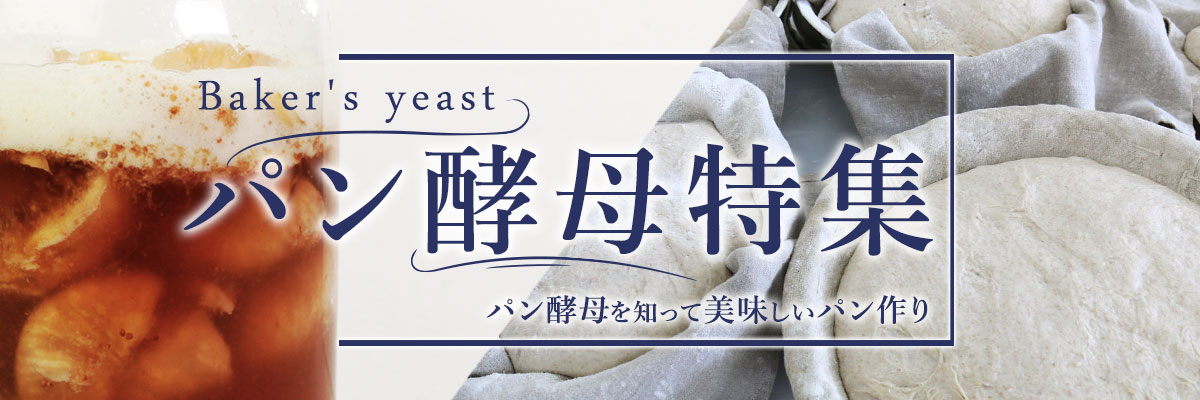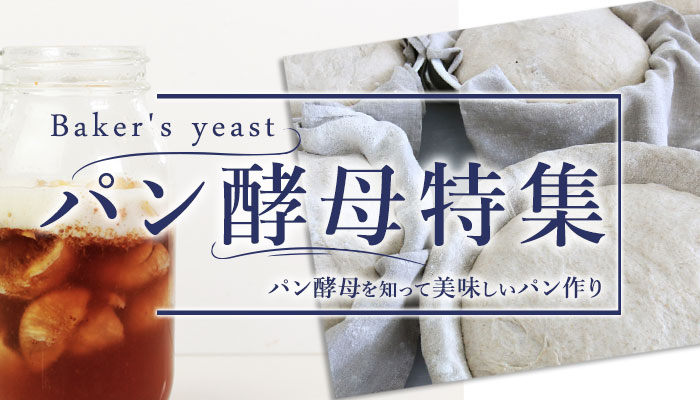有機ココアパウダーでつくる、
自家製ココア酵母
ココアパウダーを使って酵母を起こしてみませんか?
カカオを原料とするチョコレート同様に、実は発酵食品でもあるココアパウダー。
チョコレートやココアの製造工程において、チョコレートならではの甘く豊かでまろやかな香りを引き出す為に、原料となるカカオ豆の実をしっかりと発酵させることが欠かせません。
ドライフルーツや果物から作る酵母とは違って、発酵具合の見極めが少し難しいですが、ゆっくりと時間をかけて発酵させてつくるココア酵母を使って作るパンは、カカオの風味がしっかりと残る他にはない味わいが楽しめます。
カカオを原料とするチョコレート同様に、実は発酵食品でもあるココアパウダー。
チョコレートやココアの製造工程において、チョコレートならではの甘く豊かでまろやかな香りを引き出す為に、原料となるカカオ豆の実をしっかりと発酵させることが欠かせません。
ドライフルーツや果物から作る酵母とは違って、発酵具合の見極めが少し難しいですが、ゆっくりと時間をかけて発酵させてつくるココア酵母を使って作るパンは、カカオの風味がしっかりと残る他にはない味わいが楽しめます。
作り方
1.下準備
・瓶の本体とフタを煮沸消毒しておきます。
・ぬるま湯にはちみつを混ぜ溶かしておきます。
【シェフのワンポイントアドバイス】
雑菌やカビの発生を防ぐために、スポンジや布巾を使って洗ったり拭いたりしないようにしましょう。

2.【発酵エキス】
煮沸して清潔にしておいた瓶に、材料を全て混ぜ合わせて加えフタをします。
通気性が良く出来るだけ温度湿度の変化の少ない場所に保管します。
適正温湿度条件
温度:25~30℃ / 湿度:約60%
1日に1回はフタを空けてガスを抜き酸素を取り込むことで発酵を促進させます。
1日目

2日目~

表面に数点、気泡が現れます。
3日目

気泡の数が増え、全体に細かな気泡が現れます。
ほのかに発酵臭が感じられるようになります。
4日目

容器内にガスが十分に発生し、全体に力強い気泡が現れます。
※酸っぱい匂いや刺激臭、異臭がする場合は雑菌が繁殖したことが考えられます。
完成

完成した発酵エキスは、フタを空けた際に大きな音と共に発泡し、
甘いチョコレート香と発酵臭が感じられます。
1日置いてから、全体を練り混ぜクリーム状にしておきます。
《 失敗例 》
瓶の開閉時の際など、結露や水分などが混入するとカビが生えやすくなります。
写真のように、カビが部分的であればその部分を取り除き掻き混ぜてください。
翌日、カビが発生していないようであればそのまま継続して大丈夫です。

3.【酵母種】
1日目
ボウルに小麦粉を入れ、発酵エキスを徐々に混ぜ合わせていきます。
全体が味噌くらいの硬さになるまでを目安に発酵エキスを加えていきます。
※表面に分量外のココアパウダーを振りかけることで発酵具合の確認がしやすくなります。
【シェフのワンポイントアドバイス】
梅雨時期や夏場の湿度が高い季節などでは、塩を2%程度加える事で雑菌の繁殖を防ぐ効果があります。

乾燥しないようにビニール袋を被せ25~30℃で2~3時間常温発酵させます。
発酵後、ビニール袋に被せたまま翌日まで冷蔵庫(5℃)に入れておきまます。
※ビニール袋でなくラップをかける場合は、表面に空気穴を数か所空けてください。2日目以降
| 材料 | 2日目 | 3日目 | 4日目 |
|---|---|---|---|
発酵種 |
1日目の発酵種 |
2日目の発酵種 |
3日目の発酵種 |
水 |
発酵種に対して |
発酵種に対して |
発酵種に対して |
小麦粉 |
発酵種に対して |
発酵種に対して |
発酵種に対して |
塩 |
発酵種に対して |
発酵種に対して |
■共通工程
ボウルに発酵種、水を入れてよくふやかしておきます。
■2日目
小麦粉を加えよく混ぜ合わせます。
表面を平らに均し、乾燥しないようにビニール袋を被せ25~30℃で2~3時間常温発酵させます。
発酵後、ビニール袋に被せたまま翌日まで冷蔵庫(5℃)に入れて寝かせておきます。
■3日目
小麦粉と塩を加えよく混ぜ合わせます。
表面を平らに均し、乾燥しないようにビニール袋を被せ25~30℃で2~3時間常温発酵させます。
発酵後、ビニール袋に被せたまま翌日まで冷蔵庫(5℃)に入れて入れて寝かせておきます。
■4日目
小麦粉と塩を加えよく混ぜ合わせます。
表面を平らに均し、乾燥しないようにビニール袋を被せ25~30℃で2~3時間常温発酵させます。
発酵後、約2倍の大きさに膨らめば完成です。
2日目


発酵後、表面全体がひび割れて開き始めます。
3日目


発酵後、約1.5倍~2倍に膨らみます。
4日目


完成
※カビや異臭がしないか確認しましょう。
【シェフのワンポイントアドバイス】
発酵種をつくる工程では、過発酵にならないように注意が必要です。
捏ねる工程の無い発酵種はグルテン形成のないまま発酵するので、その場の温湿度環境によっては過発酵しやすくなります。
過発酵した種でパンをつくると酸味が強く、また発酵力も弱いので膨らみの少ないパンに仕上がります。